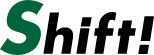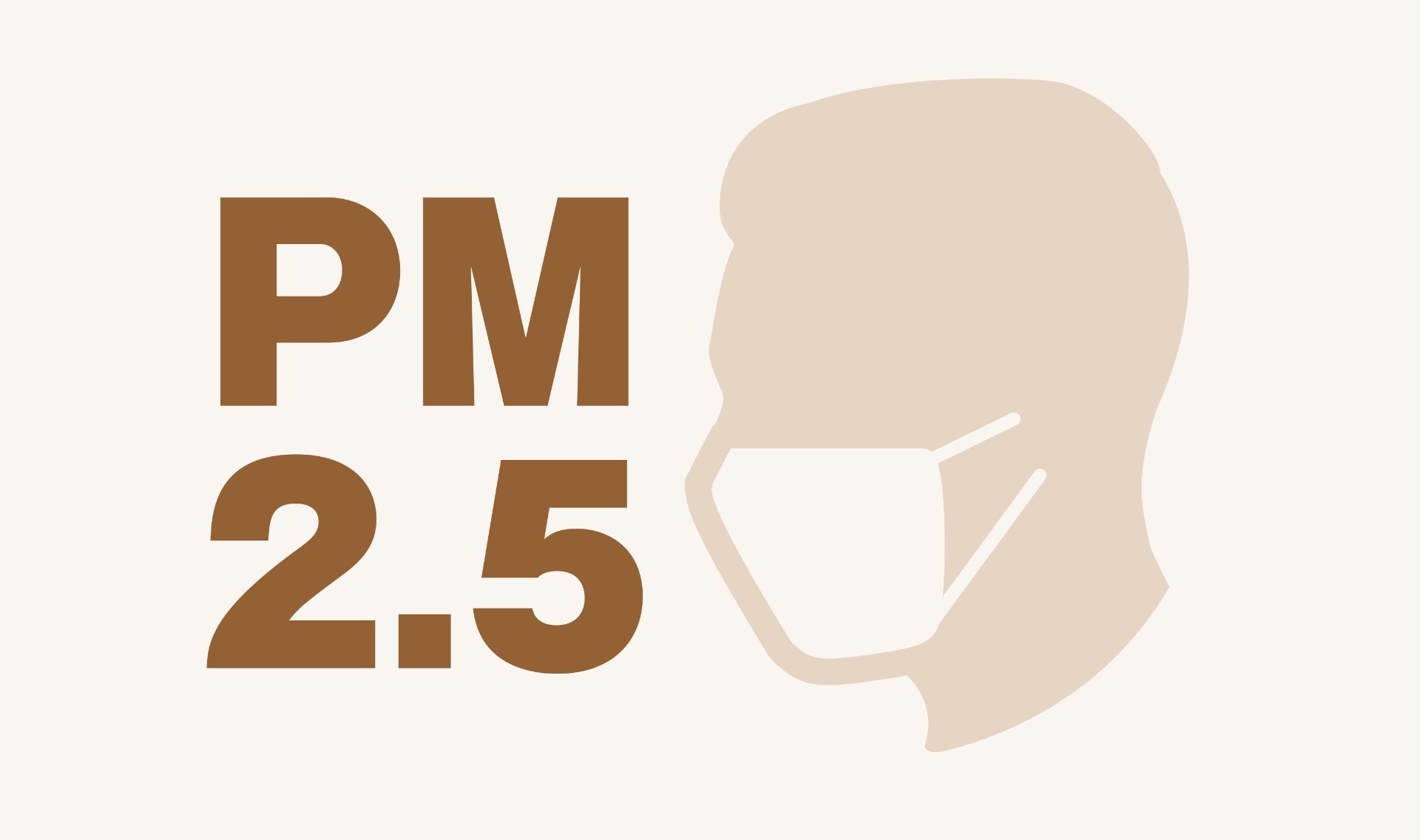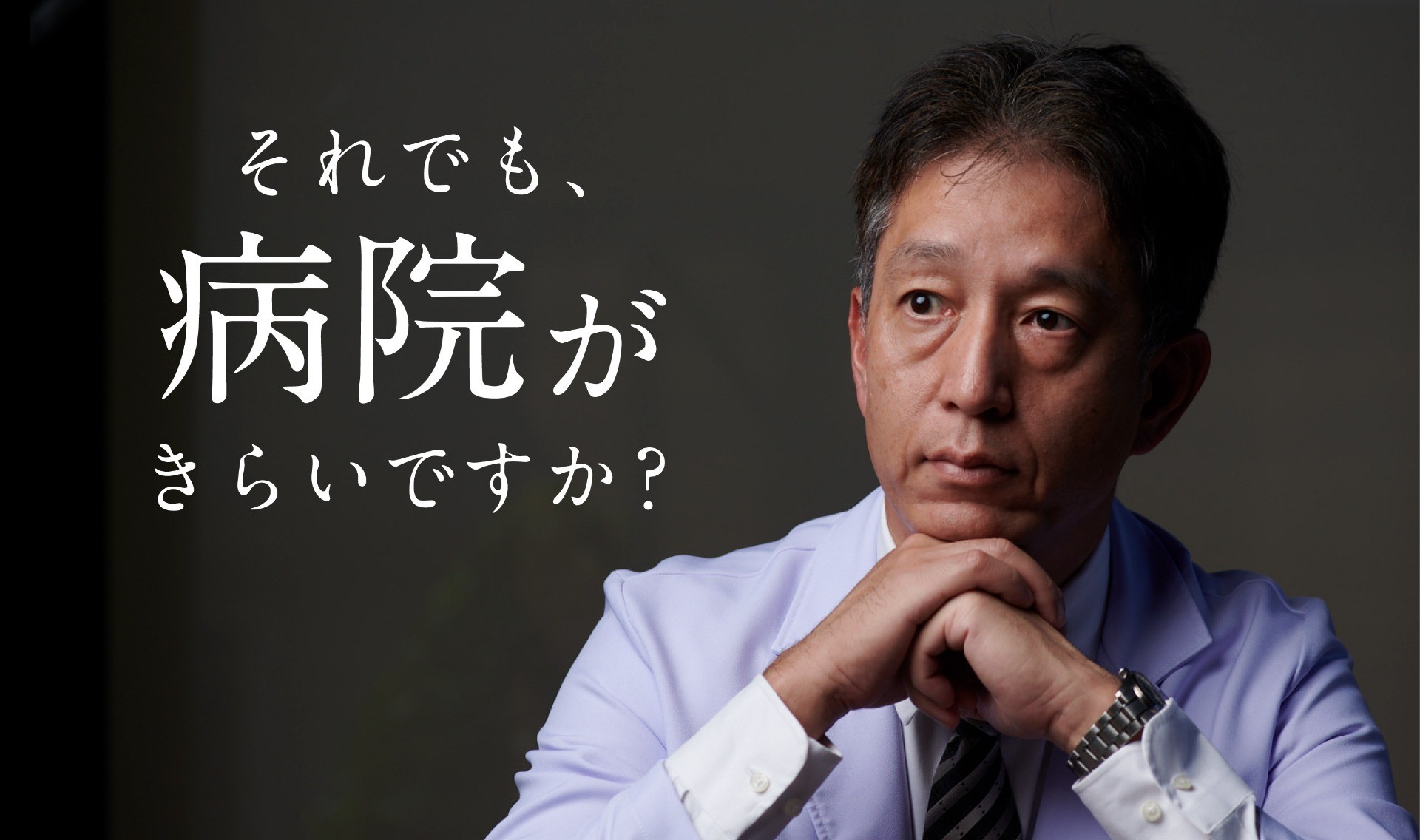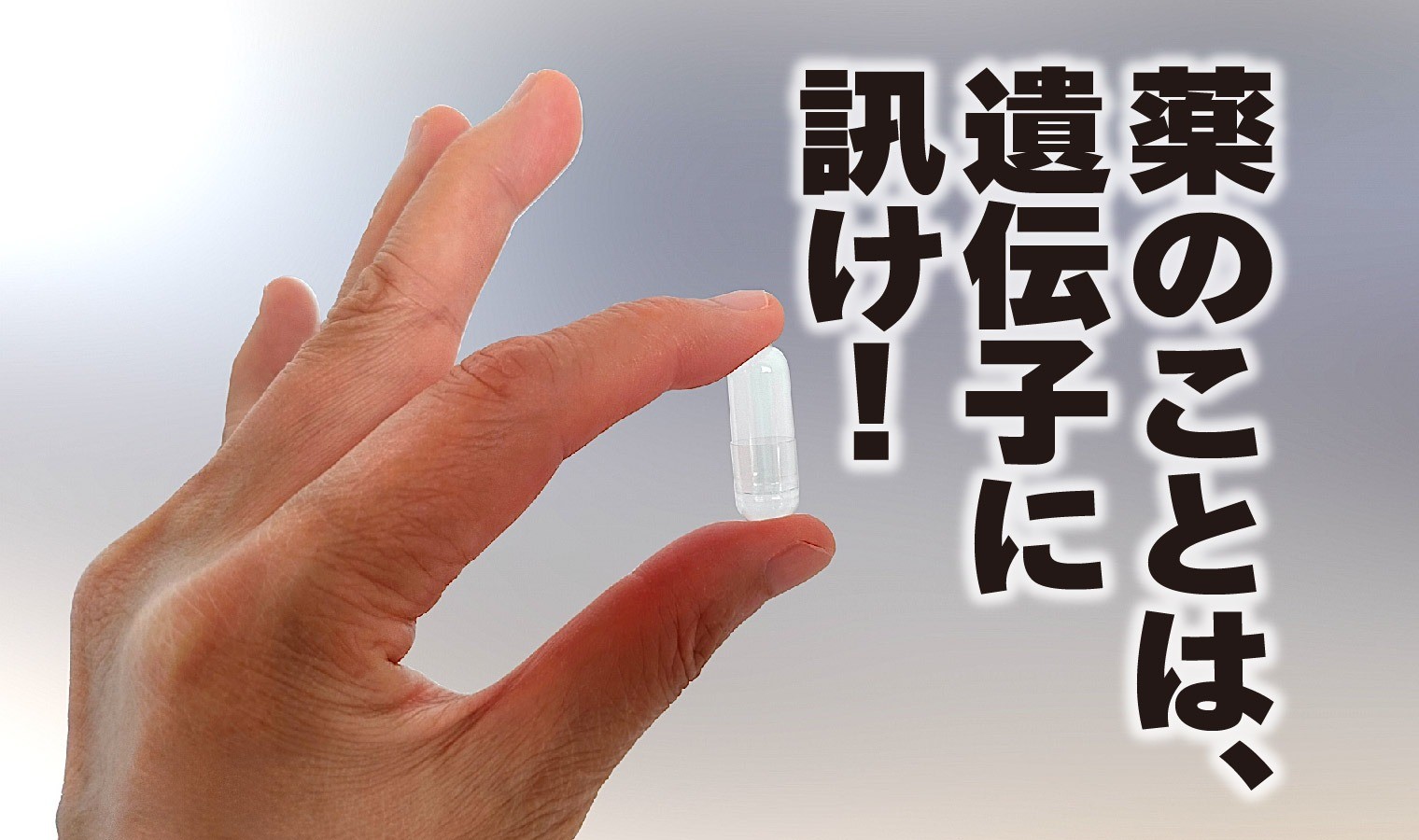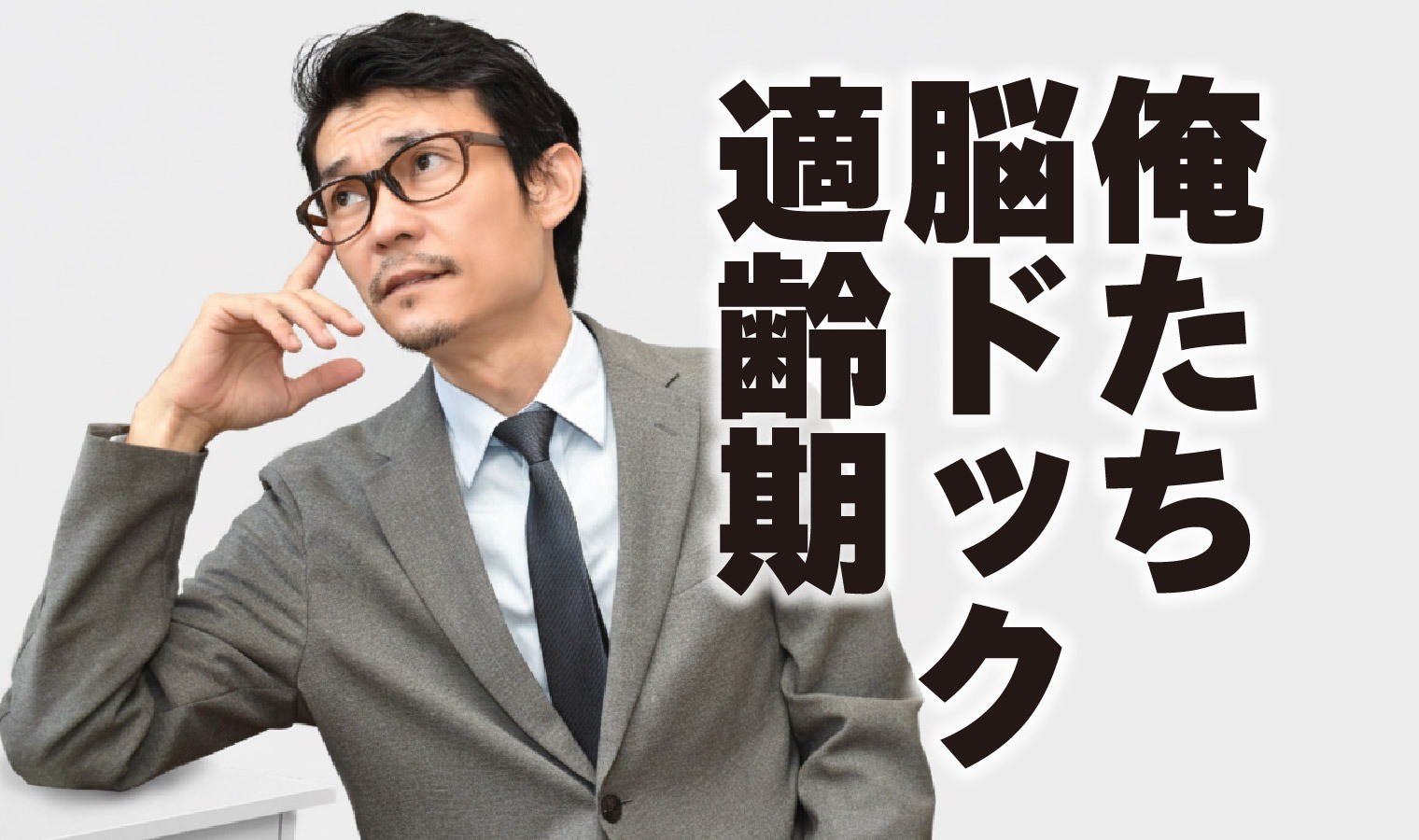日本は大丈夫だよね
総裁選の騒ぎをボーっと見ていて、まるで臓器移植の拒絶反応みたいだなと思った。それは体が自分ではないものを異物とみなして排除しようとする防衛機構で、命を救うはずの移植が時に命取りになるのは、自己と他者の境界があまりに厳格であるからだ。
昨今の世相を見渡してみると、他者へのアレルギーともいえる拒絶の空気が濃くなっているように感じる。政権交代のたびに前政権をまるで異物のように排除するのは海の向こうの国だけではなくなっているし、SNSの炎上、排外的な言説を見聞きするにつけ、まるで社会全体が過敏な免疫反応を起こしているようにも見える。
そこでカギとなるのはタイを経験している私たちだ。日本とは異なる言葉、価値観、完璧に理解できなくても、受け入れることは可能であることを私たちは身をもって経験している。よく考えてみると異物である日本人を受け入れてくれているのはタイのほうだったりする。
そう、臓器移植は他者のいのちを自分の中に取り込む行為だ。その奇跡的な医療は、拒絶のリスクを乗り越えた先にある。拒絶反応を抑えるために医療では免疫抑制剤を使う。社会においてそれにあたるのが共感や対話なのだろうと思う。しかし、対話はいうがやすし、行うは難し。互いに言葉を交わすことはできても、本当に相手の立場に立つのは簡単なことではない。
医療の現場でも、患者の語る不信や不安、心身の痛みを聴くことは、技術以上に姿勢が問われる。異文化の中で暮らすこともまた、日々の対話の積み重ねであり、時に通じ、時にすれ違うものだが、それは拒絶につながるものではなく、移植の成功と同じように緩やかに融合していけるものだと思う。完璧な同化を求めず、違いをそのまま受け止める。その柔らかさが今の時代には必要なのではないだろうか。
南 宏尚(みなみ ひろたか)
大阪の高槻病院で長年小児・新生児医療の第一人者として臨床・研究・教育に携わる。サミティベート病院では医療相談やセミナーで邦人社会をサポート。現在は出張ベースで相談やセミナーを継続中。齢50にして長年の不摂生を猛反省、健康的生活に目覚めるも、しばしばリバウンドや激しすぎる運動で体を壊しがち。